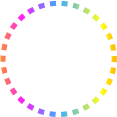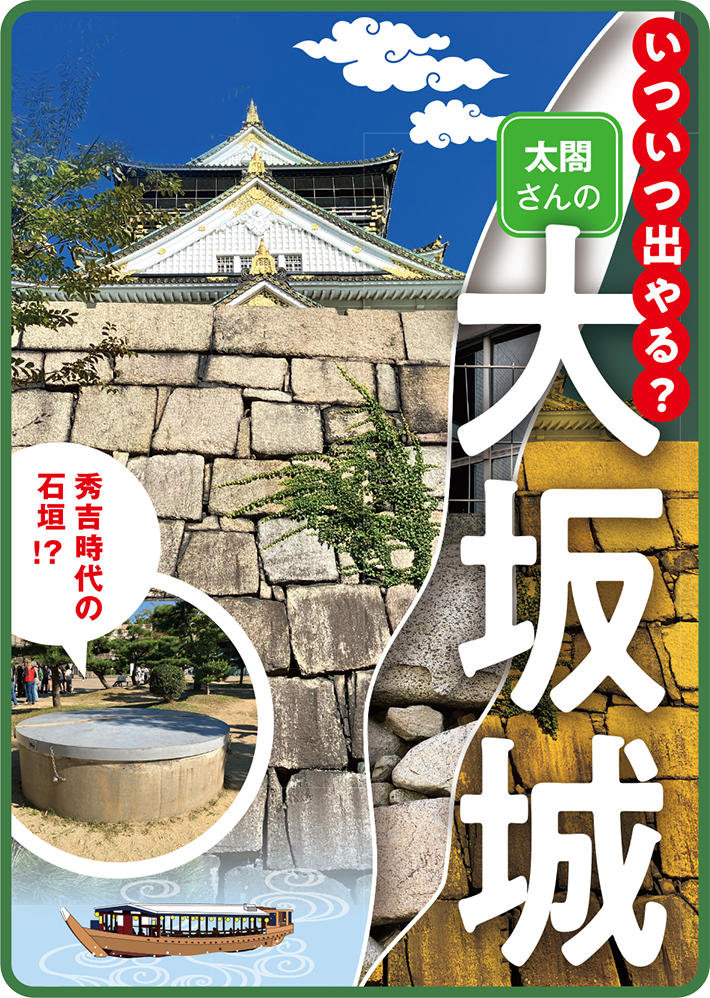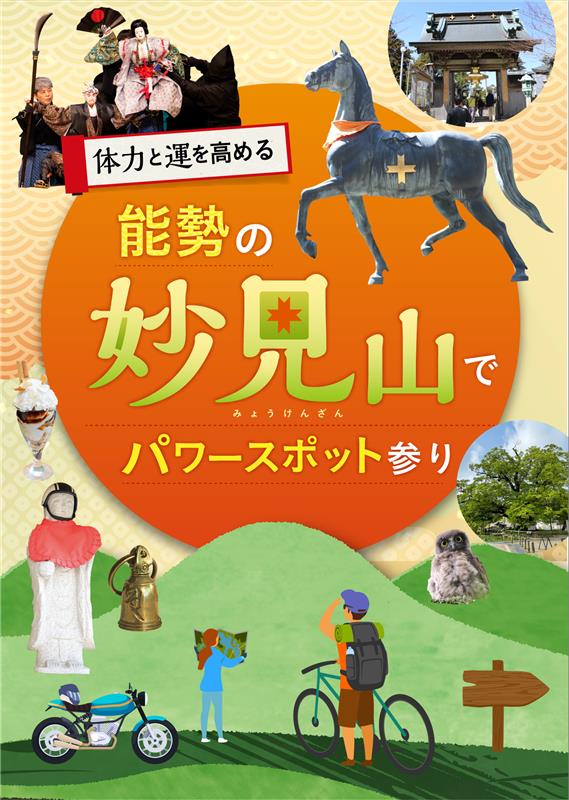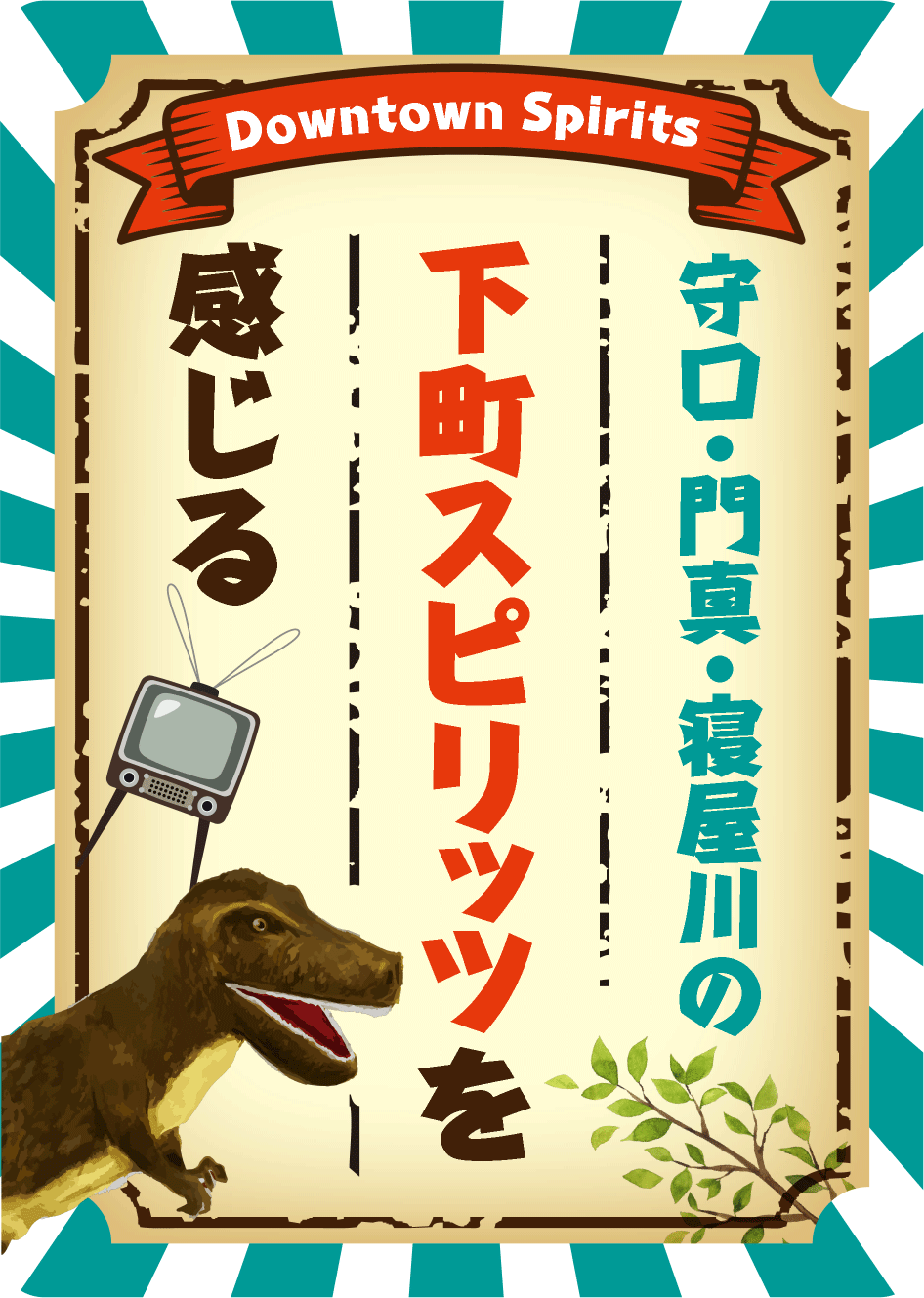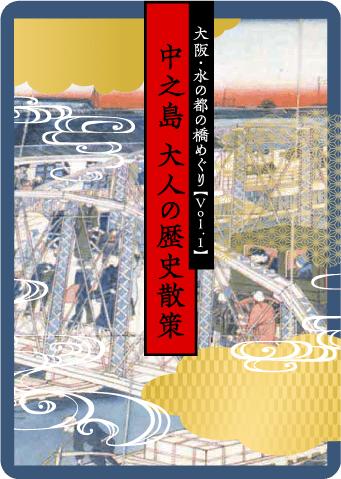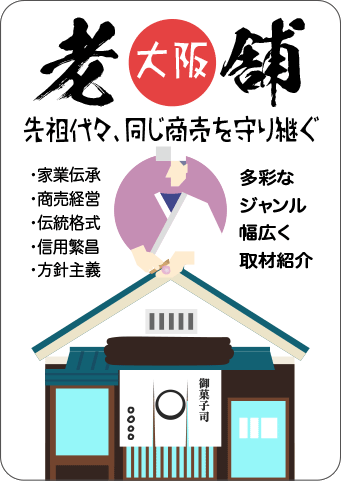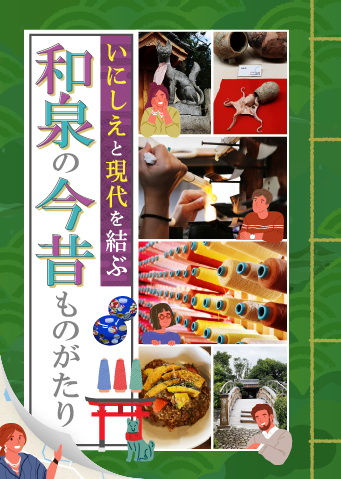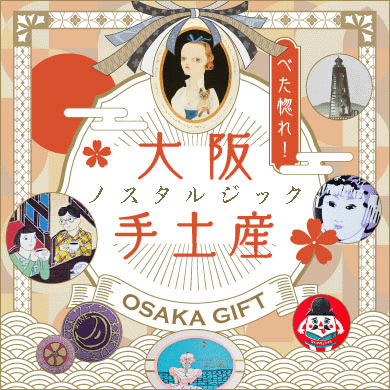堺市にある南宗寺(正式には南宗禅寺)は1557年、戦国大名・三好長慶が創建した。ここには国指定重要文化財の建築として、仏殿・山門(甘露門)・唐門の3つが登録されている。1653年〈承応2〉建立の仏殿は、禅宗様式の技法を用いた、大阪府下で唯一の「仏殿」形式。桁行・梁間各三間、入母屋・本瓦葺、裳階(もこし)付。天井には有名な「八方睨みの龍」がある。





1647年〈正保4〉建立の山門(甘露門)は、2層形式の楼門、入母屋・本瓦葺。上層軒裏の扇垂木など、禅宗様の技法が見られる楼門だ。江戸前期、仏殿と同時期建立とみられる唐門は本瓦葺の小規模な薬医門風の門。かつて境内にあった東照宮に通じた「表門」と伝わる。


さらに南宗寺の庭園(方丈庭園)は国指定名勝。平庭の枯山水で、上部の枯滝・石橋と平場の石組(横石を据えた意匠)が調和する構成。江戸初期の作庭で、古田織部作と伝わる。 徳川家康ゆかりの伝承として、境内には家康の墓と伝わる墓石が残されている。これは「大坂の陣で傷を負った家康が堺に落ち延び当寺で没した」という伝承だ。真相は分からないが、のちに秀忠や家光がここを訪れている痕跡も寺には残っているといわれ、一定の裏付けがあるといえる。少なくとも、大坂の陣後の家康が影武者だったか、ここで戦死したのが影武者だったのか、どちらかの可能性がある。(かの)
- 南宗寺
- 住所:大阪府堺市堺区南旅篭町東3丁1-2
- アクセス:阪堺電気軌道阪堺線 御陵前停留場下車、徒歩5分
投稿されたコメント
投稿フォーム