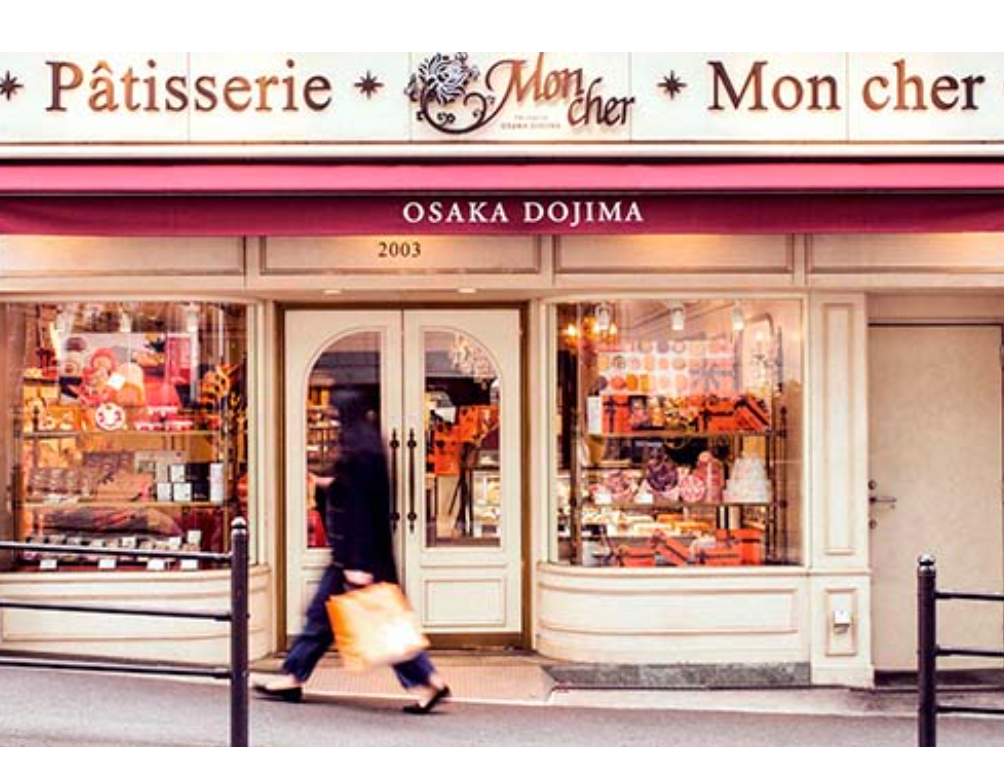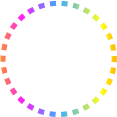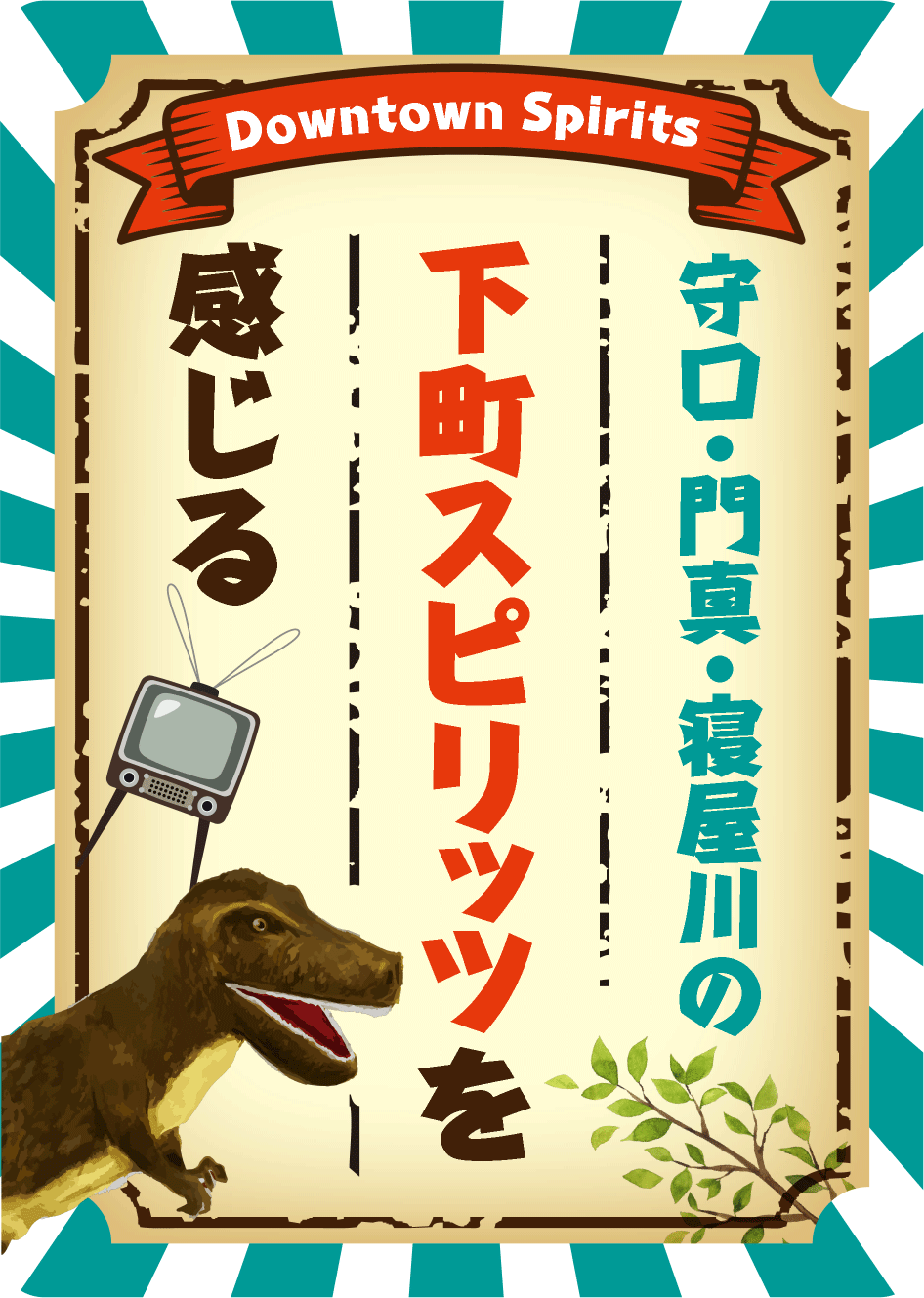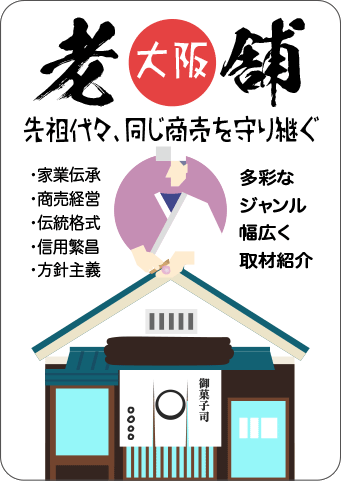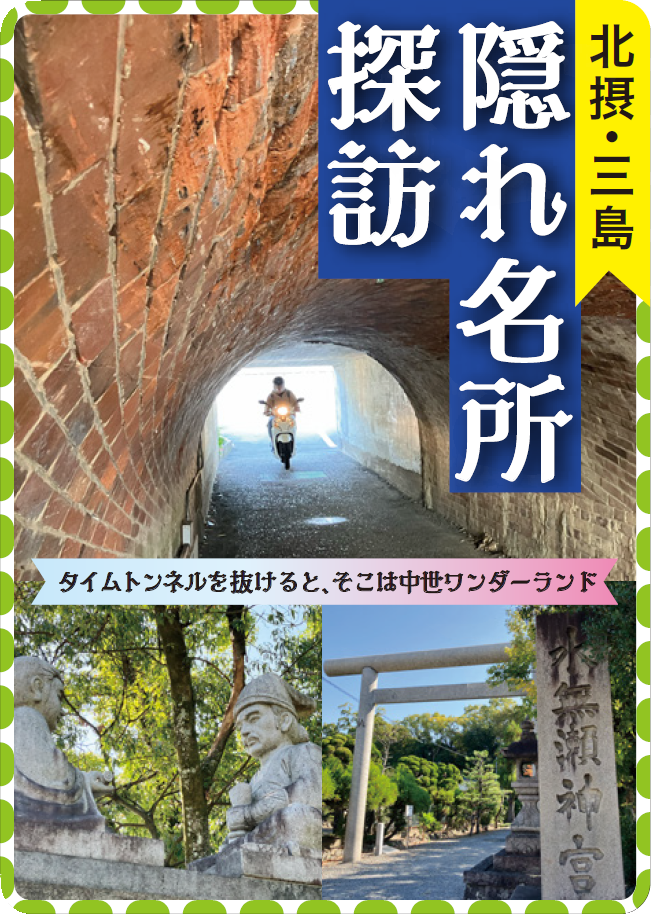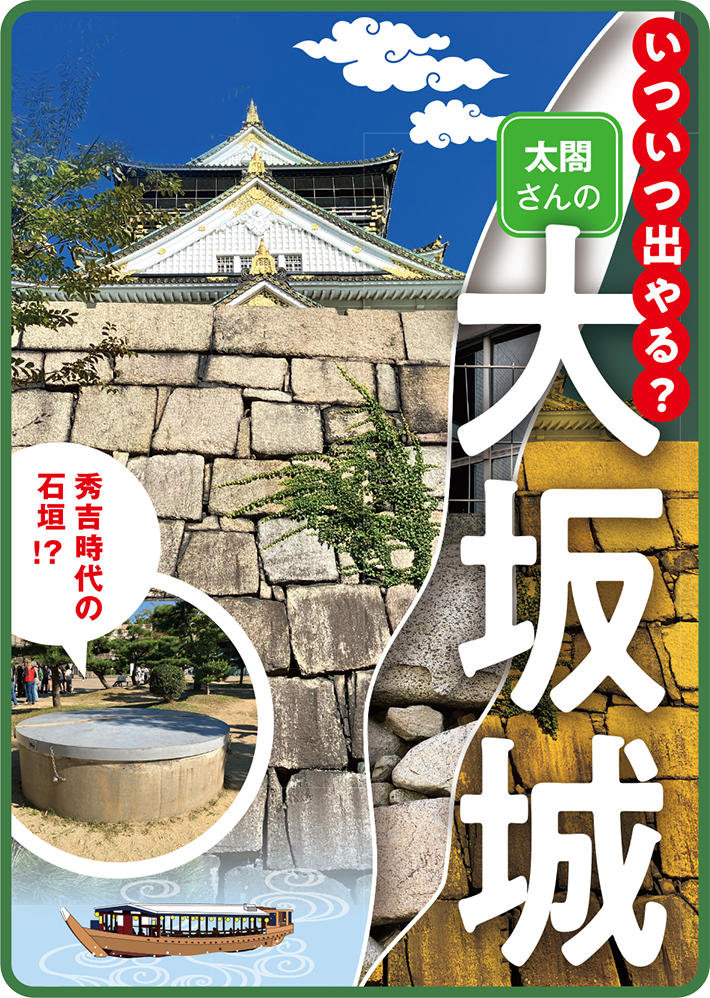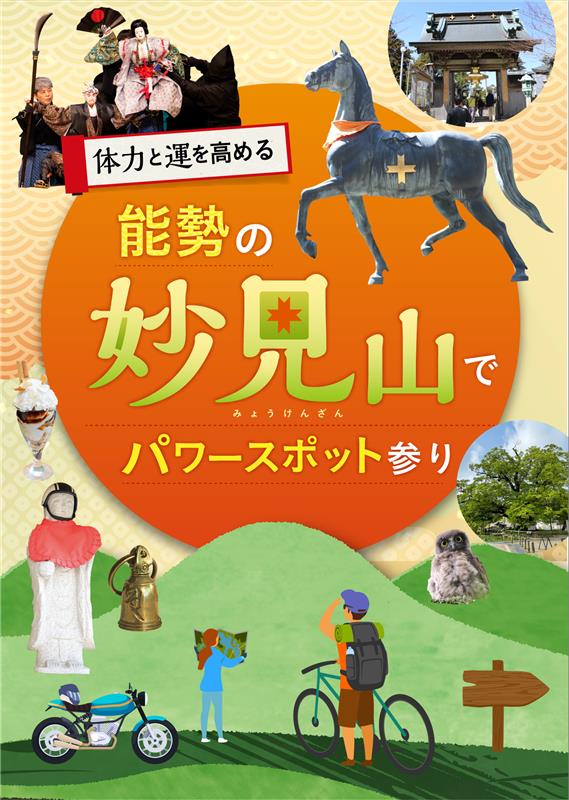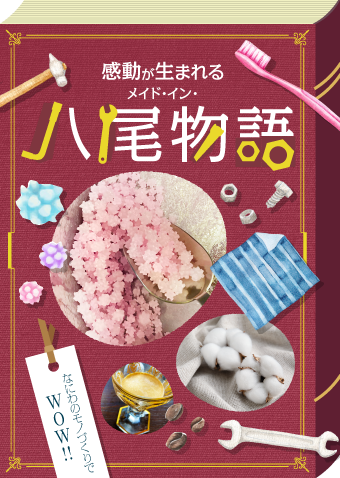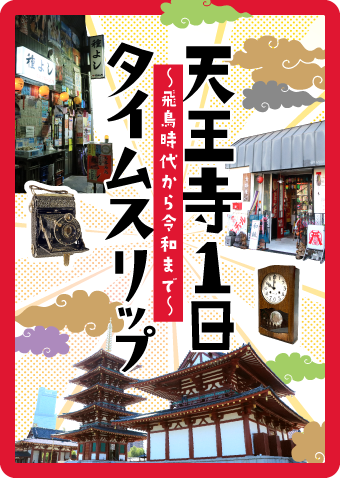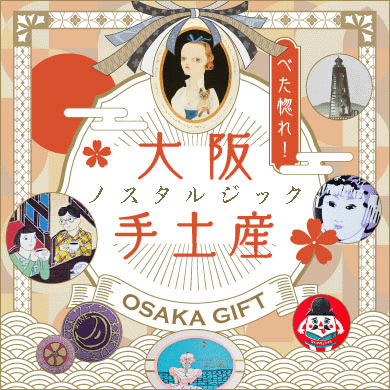百年の時を超え140種の桜が誘う、文明開化の香りとともに歩く桜路。



●概要:桜の通り抜けは造幣局の南門(天満橋側)からスタート。北門(桜宮橋側)までの約560メートルの通路脇に桜がびっしりと植えられている。現在では142品種・約340本の多彩な美を放つ桜を求めて世界中から観光客が集う。その8割が八重桜(里桜)とあって、多くの樹は花弁数が多く実に華やか。中には50枚もの花弁をつける品種もあるそう。色も白色、淡紅色、淡桃色、紅紫色、黄色など多様で、手毬のように密生して咲く花もあれば、幹にまといつくように咲く花も。樹の説明や命名の由来を見ながら歩くと、その多彩さをより楽しめる。昼間の通り抜けは、青空に映える桜の色彩の優美さと、陽光に輝く花の可憐さを、ほのかな桜の香りとともに堪能できるひとときだ。


●夕暮れの通り抜け:日没後はぼんぼりの明かりが桜を照らし、幻想的な雰囲気に。晴天であれば言うことはないが、今回はあいにくの天候で人もまばらでゆっくり見学できた。雨風に吹かれ散りゆく桜吹雪が切なくも、また違った風情が味わえてよかった。春の訪れと去り際を、しっとり満喫してほしい。



●桜の通り抜け起源:江戸時代この辺りにあった伊勢・藤堂藩の蔵屋敷の桜にまで遡る。当時の大阪には各藩が年貢米などを保管する蔵屋敷がたくさんあった。ある日、自藩の蔵屋敷に立ち寄った藩主、藤堂高虎(とうどうたかとら)は大川の対岸に見える桜ノ宮の見事な桜に感心して、蔵屋敷の敷地にも桜を植えることを命じる。その桜が庶民にも開放され、桜の季節には多くの花見客が訪れるようになったと言う。しかし、明治の廃藩置県で蔵屋敷は取り壊されることになり、当地に造幣局が開設された折に、桜を移植したそうである。そこで造幣局長の遠藤謹助が「局員だけで楽しむのはもったいない」と、1883(明治16)年に一般公開を決めた。以降、明治・大正・昭和・平成・令和と造幣局の「桜の通り抜け」として長く親しまれた。


■Information
住所:大阪市北区天満1-1-79
アクセス:大阪メトロ谷町線天満橋駅から徒歩15分
https://www.mint.go.jp/
※桜の開花時期の7日間(4月)。事前予約が必要
- 住所:大阪市北区天満1-1-79
- アクセス:大阪メトロ谷町線天満橋駅から徒歩15分