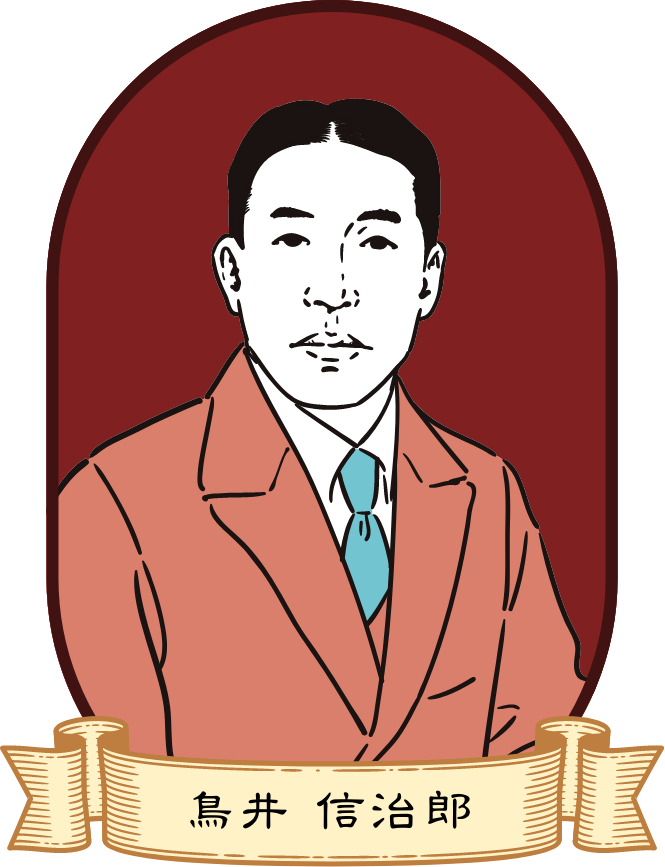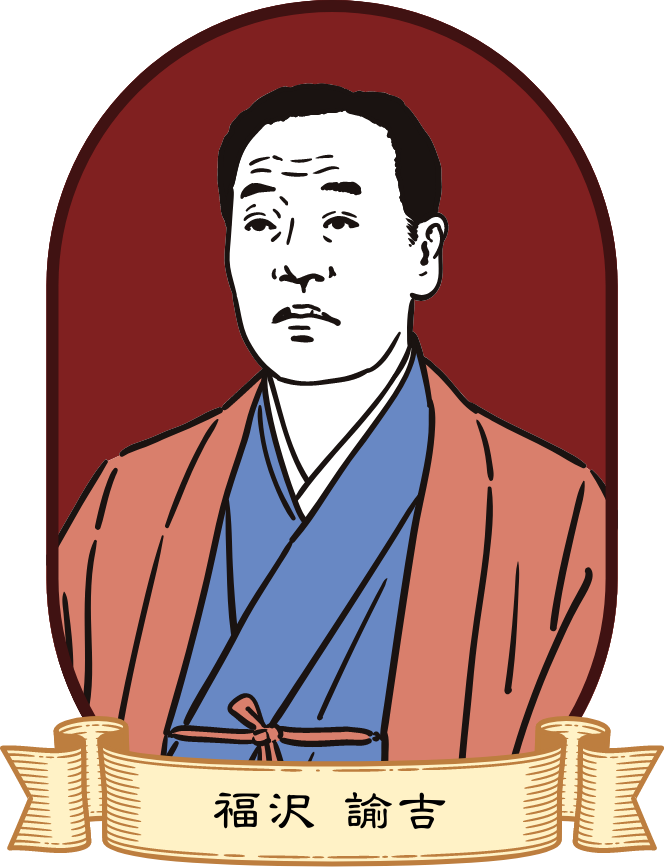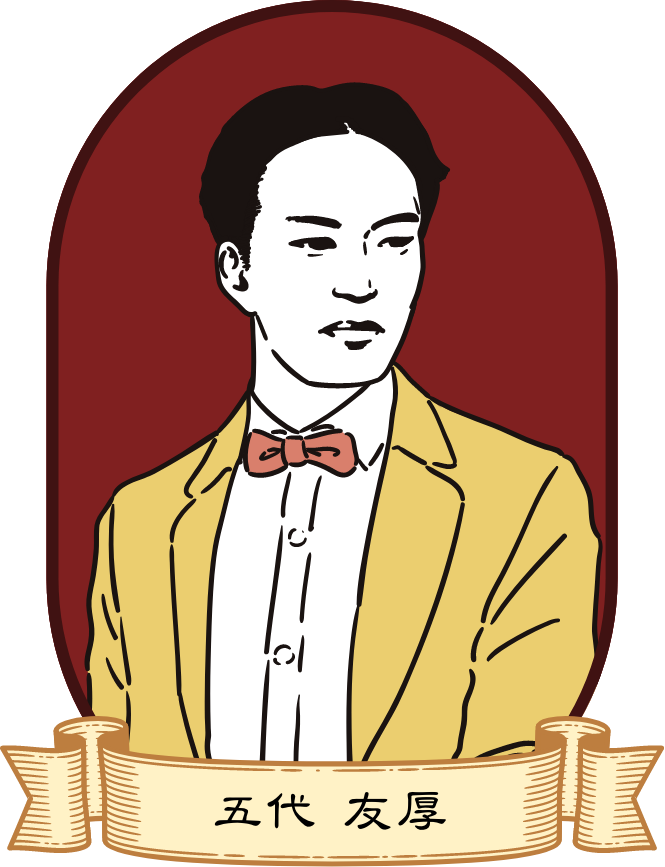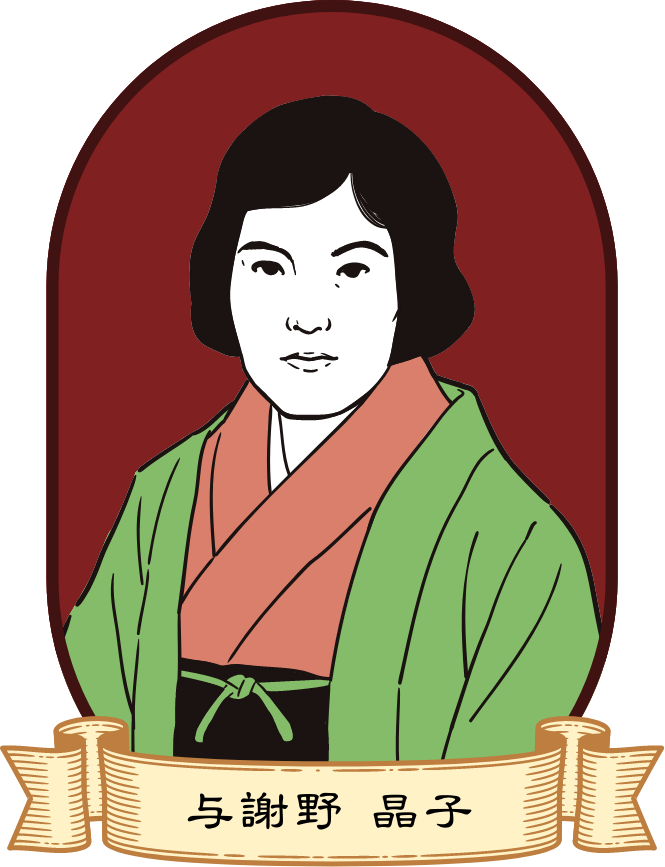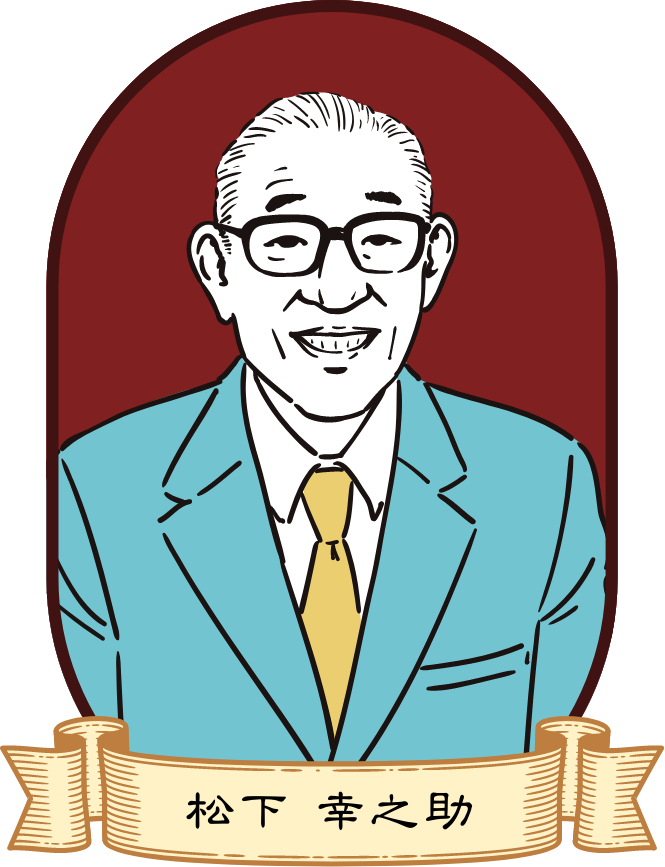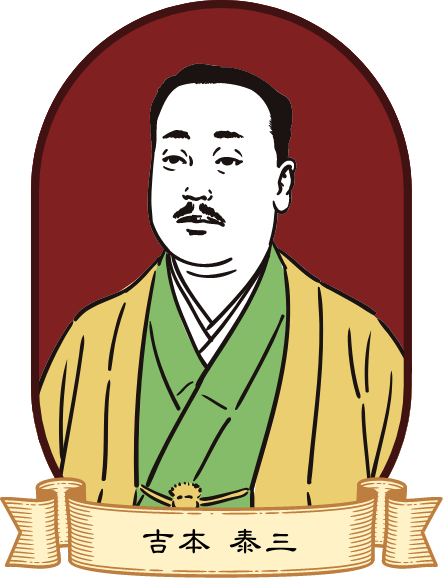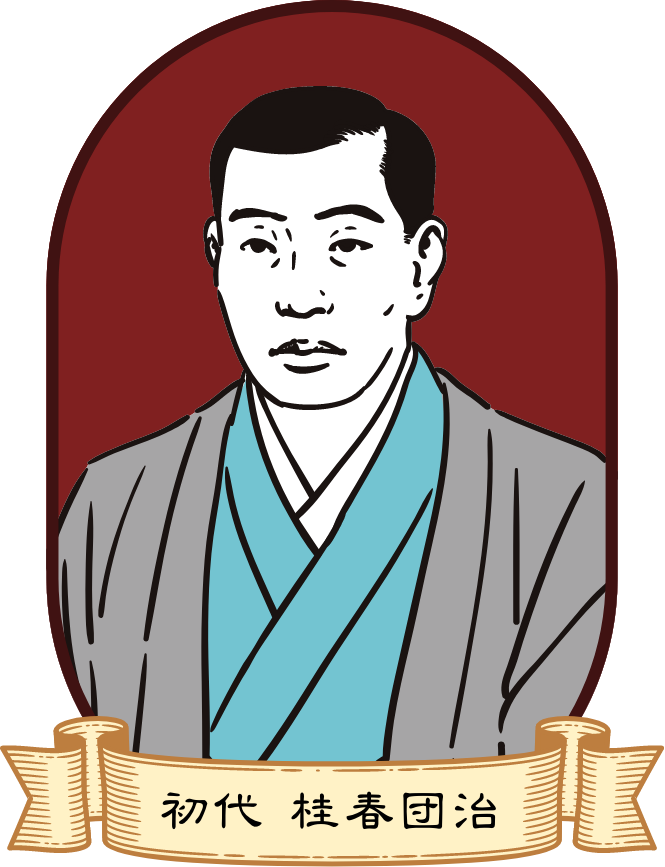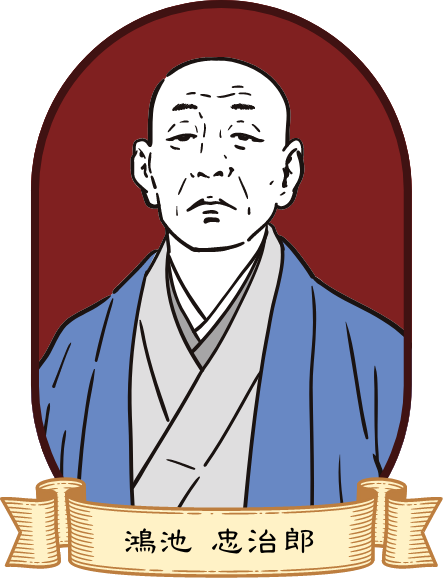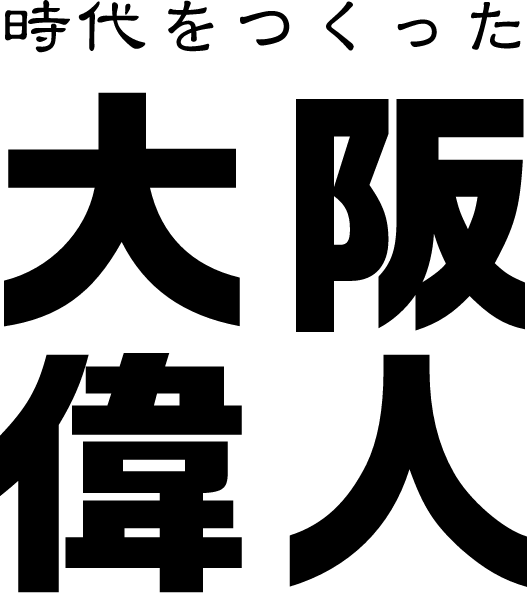
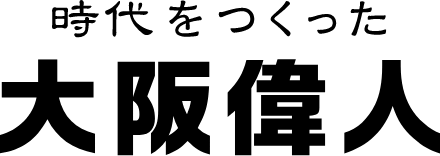
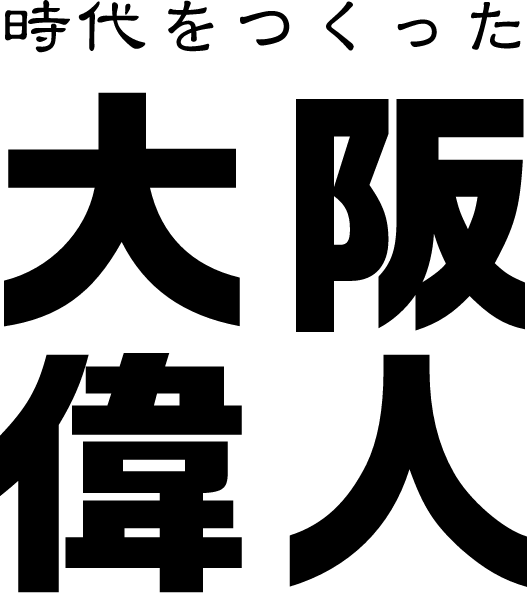
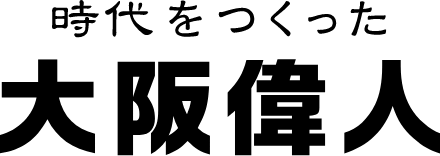
0:00
0:00
0:00
0:00



彼らの功績
-

 0:000:000:000:00
0:000:000:000:00楠木 正成くすのき まさしげ
-
鎌倉幕府討伐に貢献した『太平記』の大スター
-
1294~1336年
千早赤阪村、河内長野市
楠木正成(くすのき まさしげ)は、鎌倉時代末期から南北朝時代初期にかけて活躍した武将であり、後醍醐天皇に仕えた忠臣として知られている。兵法に優れた知将であり、少数の兵で幕府軍を何度も苦しめたゲリラ戦術の名手だった。とくに、1333年の「千早城の戦い」では、山城を拠点に幕府の大軍を撃退し、その名を全国に知らしめた。その後、建武の新政に尽力したが、南朝と北朝の対立が深まる中、1336年の「湊川の戦い」で足利尊氏の軍と戦い、壮絶な最期を遂げた。その忠誠心と勇敢な戦いぶりから、楠木正成は「忠義の鑑(かがみ)」と称えられ、明治時代には皇室への忠誠の象徴として、東京・皇居前の銅像などにもなっている。彼の精神は、今なお多くの日本人の心に深く刻まれている。 ゆかりのあるスポットはこちら 千早赤阪村で日本の原風景に出逢う
-
鎌倉幕府討伐に貢献した『太平記』の大スター
-

 0:000:000:000:00
0:000:000:000:00千利休せんの りきゅう
-
貿易港として栄えた堺から茶の湯を広めた天下一の茶人
-
1522~1591年
堺市
千利休(せんのりきゅう)は安土桃山時代の茶人で、「わび茶(侘茶)」を大成させた人物として広く知られている。本名は田中与四郎。堺の裕福な商人の家に生まれ、茶の湯の世界に深く傾倒した。華美を排し、質素で静寂を尊ぶ「わび」の精神を茶の湯に取り入れたことで、茶道を芸術・精神文化として確立させた。織田信長、豊臣秀吉に仕え、特に秀吉の側近として「茶頭(さどう)」の地位を築き、黄金の茶室を設計する一方で、わびの美学を貫いたその生き方は、今なお多くの人々を魅了し続けている。晩年は秀吉との対立により切腹を命じられるという波乱の最期を迎えたが、彼の思想と美意識は、現在の茶道や日本文化全体に深い影響を与え続けている。 ゆかりのあるスポットはこちら 南蛮文化薫る 泉州で感性を研ぎ澄ます
-
貿易港として栄えた堺から茶の湯を広めた天下一の茶人
-

 0:000:000:000:00
0:000:000:000:00豊臣 秀吉とよとみ ひでよし
-
人の心をつかみ、日本一出世した「太閤さん」
-
1537~1598年
大阪市
豊臣秀吉は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将であり、政治家である。織田信長の家臣として仕えたが、自分の力で出世を重ね、最終的には日本を統一した人物である。もともと農民の子として生まれながら、関白や太閤という高い地位にまで上りつめた、めずらしい存在である。人の心をつかむのが上手で、「人たらし」と呼ばれていた。大阪城を築き、にぎやかで美しい桃山文化を広めた文化の守り手でもある。また、国外に兵を送り、大陸へ進出しようとした軍の指導者でもあった。晩年には、次の政治をどうするかという不安を残したまま亡くなった。戦国時代の終わりと新しい時代の始まりを象徴する、歴史上の重要な人物である。 ゆかりのあるスポットはこちら いついつ出やる?太閤さんの大坂城
-
人の心をつかみ、日本一出世した「太閤さん」
-
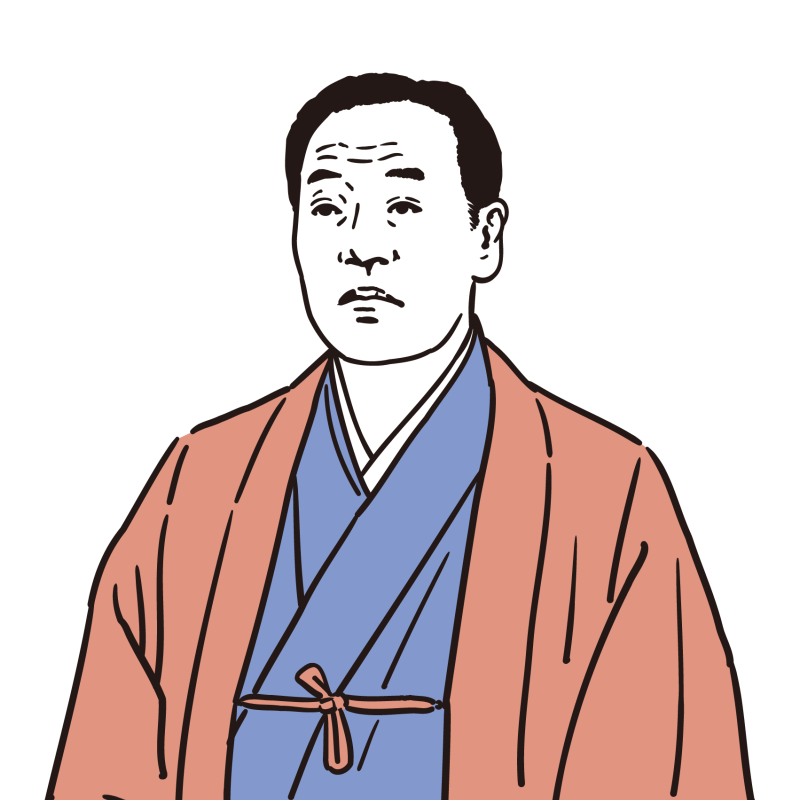
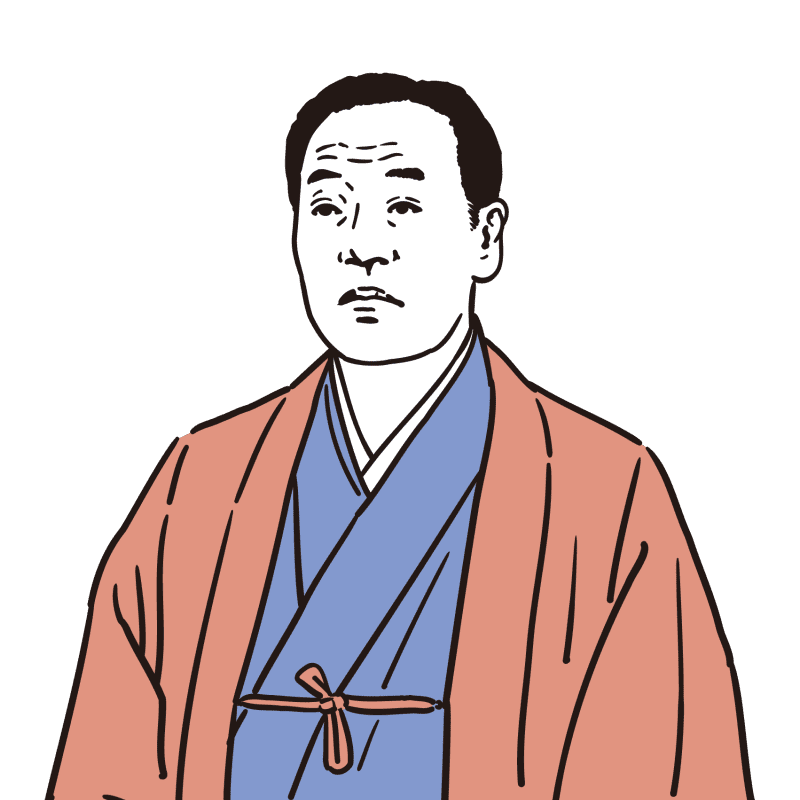 0:000:00
0:000:00福沢 諭吉ふくざわ ゆきち
-
大阪で学び、大ベストセラーで全国に学びをすすめる
- 1834~1901年
大阪市
大阪・福島生まれの諭吉は、大阪大学の前身・適塾で西洋の学問について知識を深めた。その後、海外経験を経て『学問のすゝめ』を執筆。当時の国民10人に1人が読む大ベストセラーに。1984年からは「日本国民が世界に誇れる人物」として一万円札の肖像にも描かれた。
-
大阪で学び、大ベストセラーで全国に学びをすすめる
-

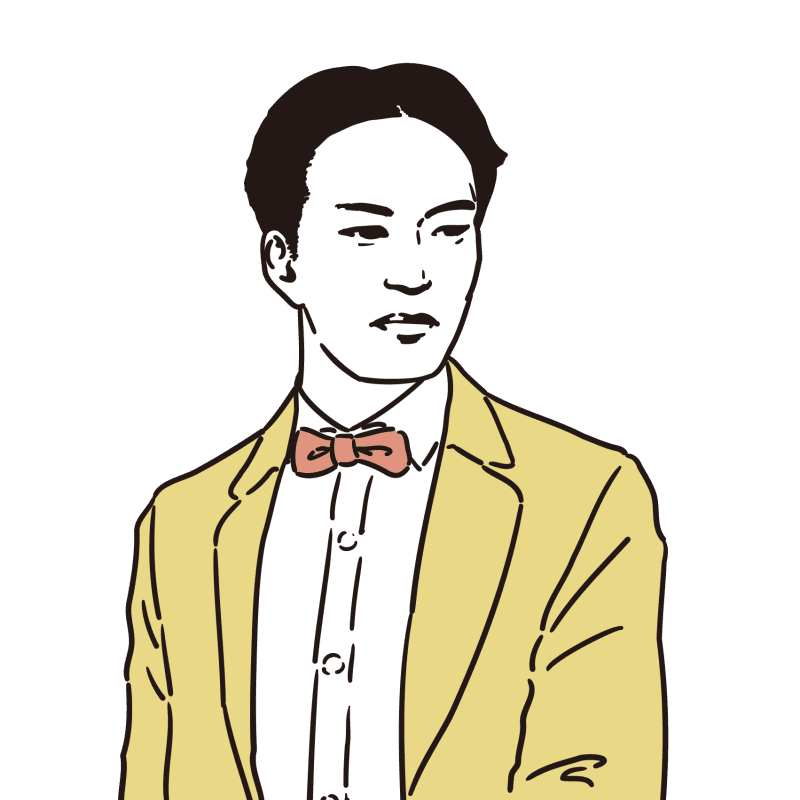 0:000:00
0:000:00五代 友厚ごだい ともあつ
-
街のおかみさんから「大阪の恩人」と呼ばれた企業家
-
1836~1885年
大阪市
幕末から明治初期に活躍した企業家。友厚が中心となり、大阪活版所・大阪株式取引所・大阪商法会議所(現在の大阪商工会議所)などを設立し、大阪の経済が大きく発展した。この業績から大阪の経済を支えた恩人とも呼ばれている。 ゆかりのあるスポットはこちら 中之島 大人の歴史散策
-
街のおかみさんから「大阪の恩人」と呼ばれた企業家
-

 0:000:00
0:000:00鴻池 忠治郎こうのいけ ちゅうじろう
-
大阪から世界へ羽ばたく企業を創立し、後の発展にも貢献
- 1852~1945年
大阪市
現在の此花区に生まれ、この地で建設業・運輸業を開始。今ではどちらも世界中に拠点を持つ大企業に。鴻池組は、淀川の改良工事(1898年)や戎(えびす)橋の建設(1925年)・架替工事(2008年)など大阪を象徴するいくつもの事業に関わっている。
-
大阪から世界へ羽ばたく企業を創立し、後の発展にも貢献
-

 0:000:00
0:000:00初代 桂 春団治かつら はるだんじ
-
独自の芸風で熱狂的に愛された、べしゃりの革命家
- 1878~1934年
大阪市
落語家の兄に影響され、初代桂文我に弟子入り。「桂我都(がとう)」と名乗ったが、1902年、二代目桂文治一門に転じ、翌年、桂春団治と改名。ひいきの客にあおられて、寒中、道頓堀川に飛び込み翌日の新聞を賑わせるなど、型破りな言動で大阪中を惹きつけた。
-
独自の芸風で熱狂的に愛された、べしゃりの革命家
-

 0:000:000:000:00
0:000:000:000:00与謝野 晶子よさの あきこ
-
文学界だけでなく世に影響を与えた情熱の歌人
-
1878~1942年
堺市
与謝野晶子(よさの あきこ)は、明治から昭和初期にかけて活躍した日本を代表する歌人・作家・女性運動家である。1878年、大阪府堺市に生まれ、本名は鳳志やう(ほう しょう)。女性の情熱や個人の愛を大胆に表現した短歌で注目を集めた。1901年に発表された初の歌集『みだれ髪』では、当時の封建的な価値観を打ち破るような、自由で官能的な愛の表現が話題となり、日本文学界に衝撃を与えた。夫であり文学者の与謝野鉄幹とともに雑誌『明星』などで活躍し、多くの若手文士を育てた。また、教育や女性の地位向上にも力を注ぎ、女学校の設立や評論活動にも積極的に取り組んだ。日露戦争中には平和を願う詩や随筆を綴り、時代を超えて響く言葉を多く残した。情熱、知性、行動力を兼ね備えた近代日本女性の先駆者であり、その作品は今なお多くの人に読み継がれている。 ゆかりのあるスポットはこちら 美とストーリーで巡る 魅惑の泉州レトロ紀行
-
文学界だけでなく世に影響を与えた情熱の歌人
-
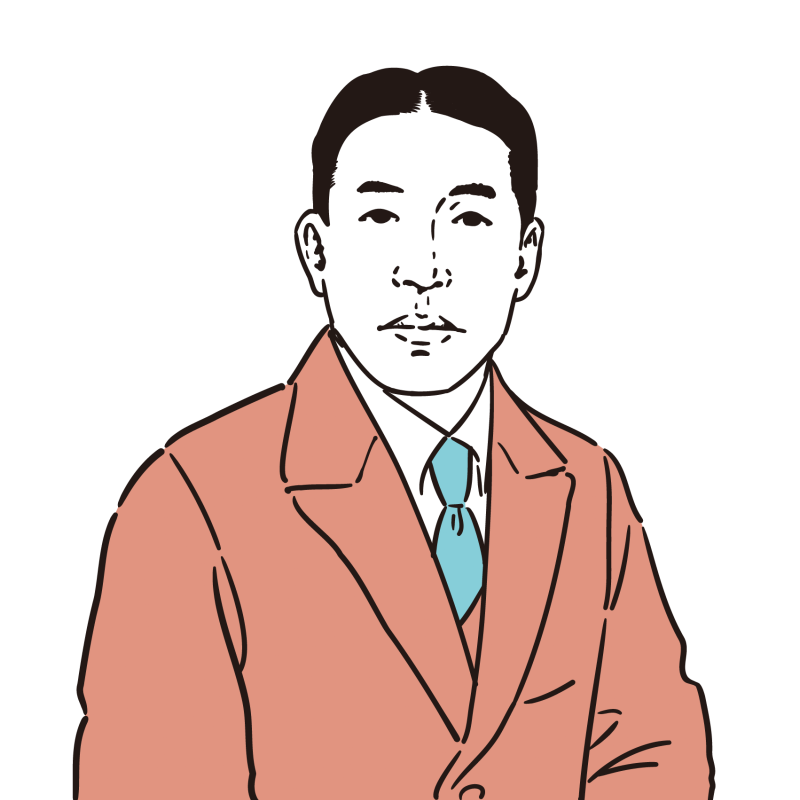
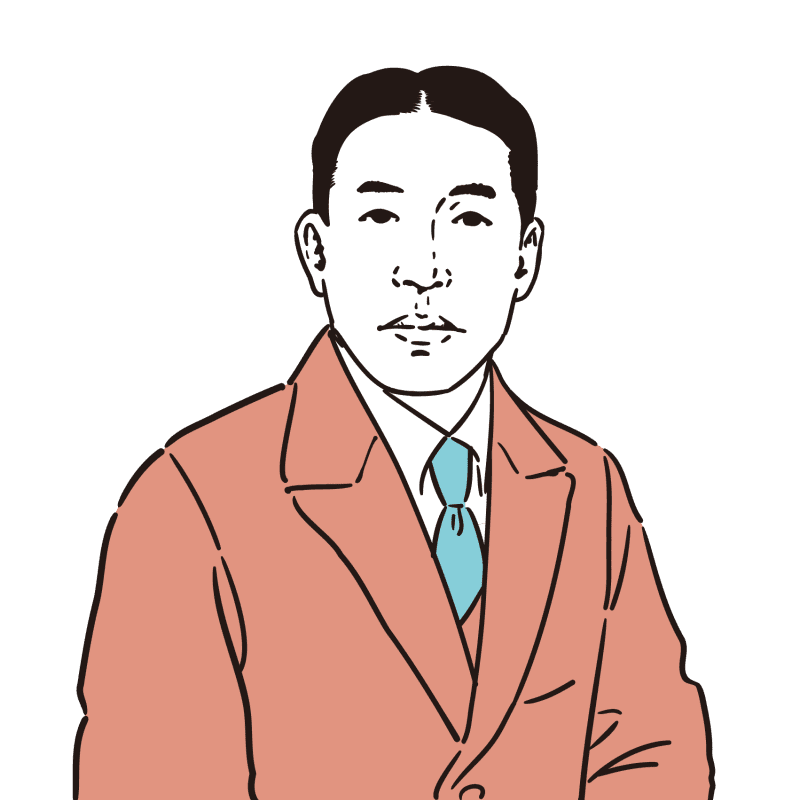 0:000:00
0:000:00鳥井 信治郎とりい しんじろう
-
日本にウイスキーを広めた「やってみなはれ」精神
- 1879~1962年
大阪市、島本町
飲料メーカー「サントリー」の創業者。洋酒という未知の分野への挑戦に反対する声にも、「やってみんことにはわかりまへんやろ」と決してあきらめず、「大阪の鼻」と呼ばれるほど鋭い嗅覚を活かし、日本初の国産ウイスキーを生み出した。
-
日本にウイスキーを広めた「やってみなはれ」精神
-
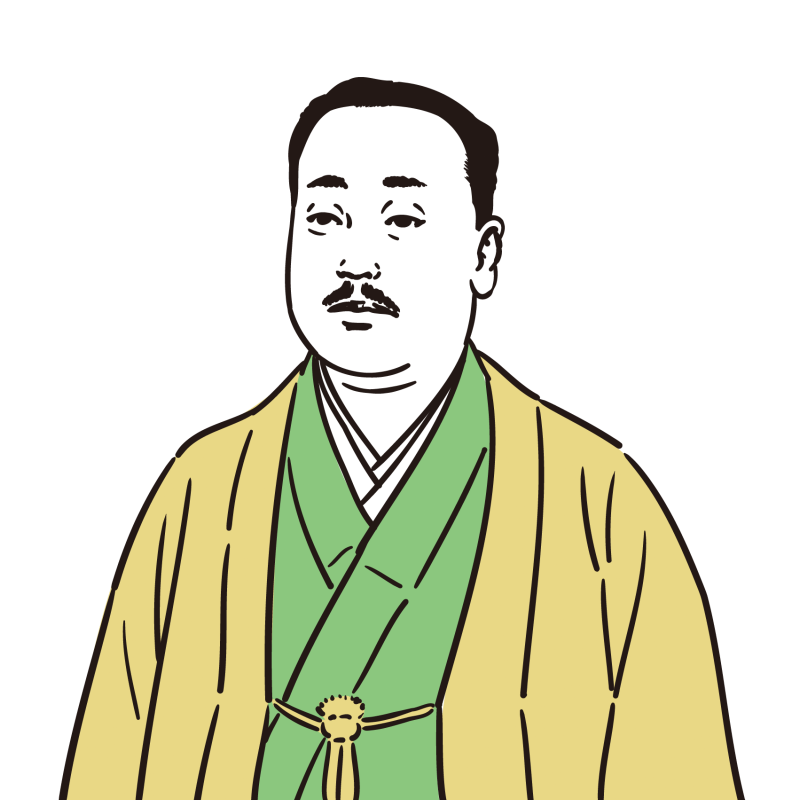
 0:000:00
0:000:00吉本 泰三よしもと たいぞう
-
妻・せいと「大阪といえばお笑い」の礎を作った男
- 1886~1924年
大阪市
明治末期に妻・せいとともに天満の「第二文芸館」を買収し寄席の経営を始め、今や日本のお笑いになくてはならない「吉本興業」を創業。「大阪といえばお笑い」という独自の文化の発展に大きく貢献し、日本のお笑い文化の発信源になった。
-
妻・せいと「大阪といえばお笑い」の礎を作った男
-
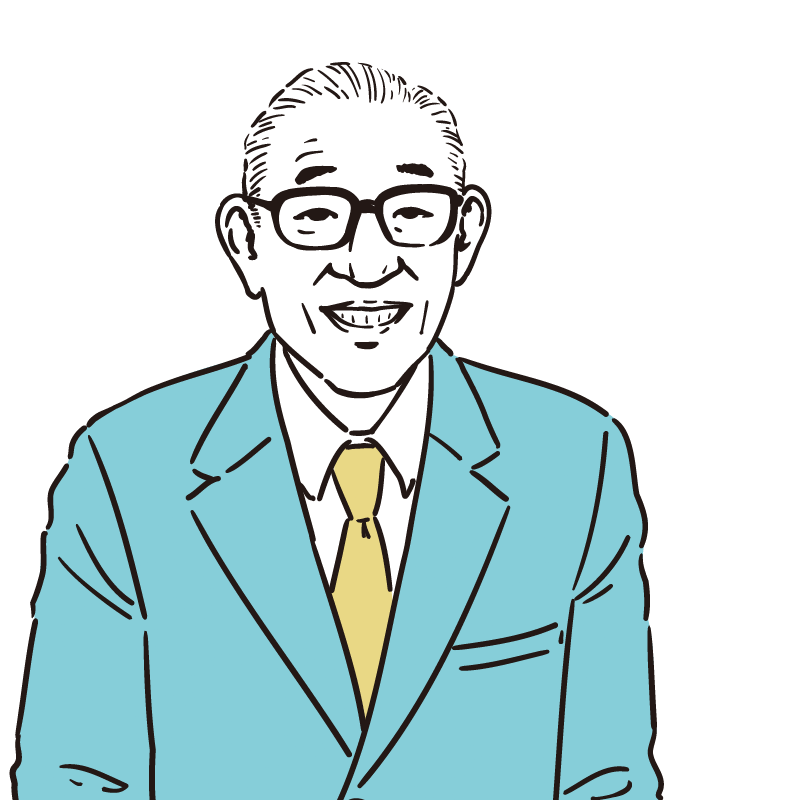
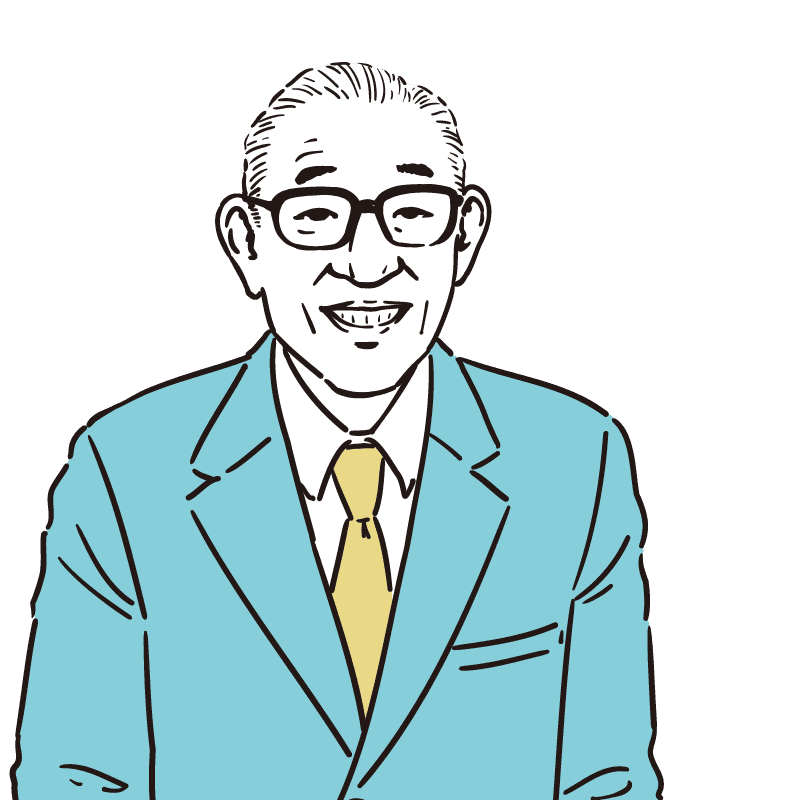 0:000:00
0:000:00松下 幸之助まつした こうのすけ
-
人類の幸福を願い、全世界に影響を与えた「経営の神様」
-
1894~1989年
大阪市、門真市
わずか9歳で丁稚奉公として大阪へ。その後、さまざまな経験を経て、1918年、パナソニックの前身「松下電気器具製作所」を創業。事業部制や週休2日制など、現代に通じる制度を国内で初めて導入し、経営の手本となる最先端の道を歩み続けた。 ゆかりのあるスポットはこちら 守口・門真・寝屋川の下町スピリッツを感じる
-
人類の幸福を願い、全世界に影響を与えた「経営の神様」
-

 0:000:00
0:000:00川端 康成かわばた やすなり
-
ノーベル賞作家の感性は大阪で磨かれた!?
-
1899~1972年
茨木市
「雪国」や「伊豆の踊子」の代表作で知られ、日本人として初めてノーベル文学賞を受賞した康成は、大阪・茨木で育った。住吉大社にある朱塗りの反橋(そりはし)は小説「反橋(そりばし)」に登場。そのそばには文学碑も置かれている。 ゆかりのあるスポットはこちら 阪堺電車で行く途中下車ぶらり旅
-
ノーベル賞作家の感性は大阪で磨かれた!?